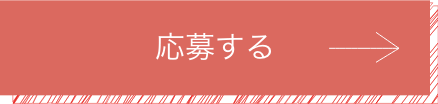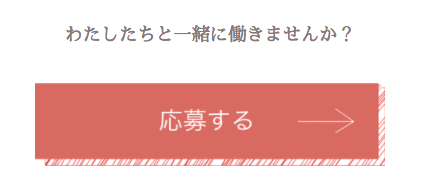社長挨拶

当社サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
THS 代表の鈴木哲郎です。
私たちの仕事は、住宅設備工事-つまり暮らしの土台に関わる仕事です。派手さはありませんが、毎日の安心に直結します。だからTHSは、目先の効率よりもまず「それは人として正しいか」を基準にします。判断に迷ったら、いつもここに戻ります。
品質は検査や最後のチェックで足すものではなく、工程の一つひとつでつくり込むものだと考えています。挨拶、養生、道具の手入れ、現場の清掃、時間の約束。小さな所作に、その現場の“本気度”が出ます。小事を丁寧にできないと、大事も守れません。
また、数字は良心の見える化です。施工寸法の保持、締結のトルク、受信レベル、作業の記録――ごまかさず共有します。数字や写真を開くことは、お客様に正しく判断していただくための、私たちの責任だと思っています。
仕上がりの“きれいさ”も、単なる見栄えではありません。見えない箇所ほど美しく整えることは、時間に対する礼儀であり、十年後の安全に対する責任です。機器の固定や防水処理の細部まで、きちんとやり切ります。
お客様の住まいに上がらせていただく以上、言葉だけでなく行いで示すことが大切です。作業前に工事の流れ、所要時間や追加費用を分かりやすくご説明し、最終的な判断はお客様にお返しします。結果だけでなく、過程の透明性まで含めて仕事だと考えています。
人の成長なくして、会社の持続はありません。先輩は背中で示し、後輩は素直に学ぶ。互いの未熟を補い合う利他の姿勢を、毎日の現場で育てていきます。技術と人柄の両方を磨くことが、最短でお客様と地域に報いる道だと信じています。
目立たずとも、根を張る会社でありたい。華やかさよりも、揺るぎない誠実さで続く会社でありたい。正道から外れず、約束に堅く、誠実に積み重ねる。THSはそんな歩みをこれからも続けます。どうぞ安心してお任せください。
THS 代表取締役 鈴木 哲郎